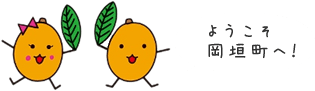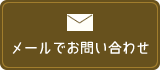インフルエンザは、毎年冬季に流行を繰り返し、健康に大きな影響を与えている感染症の一つです。
一度流行が始まると、短期間で多くの人に感染が広がります。しっかりと予防対策を立て、寒い季節を乗り切りましょう。
インフルエンザはただの風邪ではありません
インフルエンザと風邪は、症状や流行の時期が違います。
特に、抵抗力が弱いといわれている子どもや高齢者、慢性の呼吸器疾患・腎臓病・心臓病などの持病がある人は、症状が重くなりやすく注意が必要です。
インフルエンザ
- 症状 38度以上の発熱やせき、のどの痛み、全身の倦怠感や関節の痛みなどの全身症状
- 流行の時期 例年12月から3月まで
風邪
- 症状 鼻水やのどの痛みなど局所症状
- 流行の時期 1年を通してかかることがある
予防のポイント
飛沫感染や接触感染などの感染経路を断つことが大事です
飛沫感染とは、感染者の咳のしぶきに含まれるウイルスを、鼻や口から吸い込むことで感染することです。
接触感染とは、電車のつり革やドアノブなど、ウイルスが付着した物をさわった手で目や鼻、口の粘膜にふれることで感染することです。
- 外出先から戻ったら手洗いを心掛けましょう
アルコールを含んだ消毒液で手を消毒するのも効果的です。 - 適度な温度、湿度を保ちましょう
インフルエンザウイルスは、温度が低く乾燥していると長生きしやすく空気中を漂います。また、私たちののどや鼻の粘膜は乾燥した冷たい空気で弱り、感染しやすい状態になります。加湿器などを利用し、適切な湿度(50パーセントから60パーセント)を保ちましょう。 - 栄養と休養を十分取りましょう
日頃からの健康管理も重要です。栄養と睡眠を十分に取り、抵抗力を高めておくことも発症を防ぐ効果があります。 - 予防接種も重要です
予防接種は発症する可能性を減らし、もし発症しても重い症状になるのを防ぎます。流行するウイルスの型も変わるので、毎年、定期的に接種することが望まれます。
インフルエンザにかかってしまったら
症状が重くなる前に、医療機関を受診しましょう
目安として、比較的急速に38℃以上の発熱が出て、咳やのどの痛み、全身の倦怠感を伴うときはインフルエンザに感染している可能性があります。こういった症状があるときは早めに医療機関を受診しましょう。高齢者はインフルエンザや肺炎を起こしても、高熱が出ないなど、症状がはっきりしないときもあるので注意が必要です。高齢者や子ども、妊婦さん、持病のある人、重症化のサインがみられる人は、すぐに医療機関を受診してください。
重症化のサイン(子ども)
- けいれんしたり、呼びかけにこたえなかったりする
- 呼吸が速い、苦しそう
- 顔色が悪い(青白い)
- おう吐や下痢が続いている
- 症状が長引いて悪化してきたなど
重症化のサイン(大人)
- 呼吸困難、または息切れがある
- 胸の痛みが続いている
- おう吐や下痢が続いている
- 症状が長引いて悪化してきたなど
「他の人にうつさないこと」が大事です
インフルエンザの感染力はとても強く、このような対策を行っていても家庭内の他の人にうつってしまうことがあります。家族の一人一人がインフルエンザ対策に取り組むことが大切です。
学校保健安全法では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています。
- 感染症予防のため、1時間に1回程度、短時間でも、部屋の換気を心掛けましょう。
- 家族が患者さんと接するときは念のためマスクを着用し、こまめに手を洗いましょう。
「せきエチケット」を守りましょう
- せきやくしゃみが出るときは、他の人にうつさないためにマスクを着用しましょう。マスクを持っていないときは、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけて1メートル以上離れましょう。
- 鼻汁やたんなどを含んだティッシュは、すぐにゴミ箱に捨てましょう。
- せきをしている人にはマスクの着用をお願いしましょう。
注:せきエチケット用のマスクは、薬局やコンビニエンスストアなどで市販されている不織布(ふしょくふ)製マスクの使用が推奨されます。
注:マスクの装着は説明書をよく読んで、正しく行いましょう。