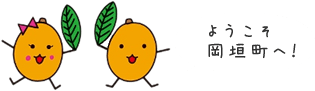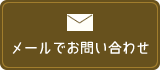申し込み時の注意事項 注:必ず確認してください
書類に不備があるときは受け付けできずに申込期限が過ぎる可能性があるため、可能な限り早めに申し込んでください。
書類が完備していないときは受け付けできません。
申し込みについて
- 受付窓口 こども未来課
- 受付期限 入所を希望する月の前月10日(10日が閉庁日のときは前開庁日)の16時45分まで
申し込み方法
下記の必要書類を受付窓口に提出してください。
注:郵送でも受け付けていますが、書類に不備があるときは受け付けできず再提出となります。可能な限り窓口に提出してください。
注:ファクスによる提出やメールなどによる電子ファイルでの提出はできません。
必要書類
次の全ての書類を提出してください。1、2はこども未来課窓口もしくは下の関連ファイルにあります。
- 入所申込書類一式(支給認定申請書兼保育所等利用申込書など)
- 保育が必要なことが分かる書類(就労証明書など)
- 保護者の個人番号を確認できる書類 例:マイナンバーカードや通知カードなど
- 身元確認書類 例:マイナンバーカード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど
注:4について、顔写真がないものは2種類必要です。
注:3、4について、郵送で提出する場合は、関連ファイル「個人番号提出に係る添付書類用台紙」に写しを貼り付けて提出してください。
注:保護者の状況により、提出する書類が異なります。詳しくは、こども未来課に問い合わせもしくは関連ファイル「保育所等入所案内」、「保育所等入所に関する注意事項」を確認してください。
入所できる人
保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に当てはまり、支給認定(保育認定)を受けた人
支給認定(保育認定)とは
提出された書類などで保護者の状況などを確認し、保育を必要とする状況にあると認定したときは、支給認定通知書を送付します。支給認定では、以下の区分や保育必要量などを決定し、支給認定通知書に記載します。ただし、子どもの3歳到達による支給認定の変更は職権で行うため、特に届け出は必要ありません。その他の理由で支給認定が変更になるときは、速やかに届け出てください。
区分
子どもの年齢に応じて、支給認定の区分を決定します。
- 2号認定 保育を必要とする満3歳以上の子ども
- 3号認定 保育を必要とする満3歳未満の子ども
保育必要量
保育を必要とする事由に応じて、保育を利用できる時間を決定します。
- 保育標準時間【保護者がフルタイム就労など】1日最長11時間(7時から18時まで)
- 保育短時間【保護者がパートタイム就労など】1日最長8時間(8時30分から16時30分まで)
注:町外の保育所等については、直接問い合わせてください 。
注:認定された保育の必要量を超えての利用は、延長保育(別途料金が必要)になります。
有効期間
保育を必要とする事由に応じて、保育を利用できる期間を決定します。
保育を必要とする事由
次のいずれかに当てはまる必要があります。
- 就労している(月60時間以上(通勤時間を含む))
- 妊娠中または出産後である(産前産後各8週間)
- 保護者の病気や怪我、心身の障がいがある
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護をしている
- 火災・風水害・震災などの災害復旧にあたっている
- 求職活動をしている(起業準備を含む)
- 就学している(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVを受ける恐れがある
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要である(4,5歳児クラスのみ)
- その他上記に類する状態として町が認めるとき
注:保育を必要とする状況を証明する書類(就労証明書、診断書、在学証明書など)が必要です。
注:同居の親族など(18歳以上65歳未満)が上記の事由に当てはまらないときは、利用調整時の優先度が下がります。
入所できる保育所等
町内の保育所等は10カ所です。下の関連リンク「町内の保育所・認定こども園・幼稚園一覧」を確認してください。
そのほかの保育所等への広域入所は、こども未来課に問い合わせてください。
入所選考
保育所等利用申込書の提出期限後、入所に関する選考を行います。選考結果は、毎月下旬に通知します。選考は、町が定めた一定の基準に基づき行っています。
保育料
令和6年4月1日から保護者利用者負担額(保育料)について、軽減額を拡大しました。ただし、保護者利用者負担額を決定する市町村階層区分によっては、軽減の拡大が適用されない階層があります。詳しくは、下の関連リンク「保育所等保護者負担金(保育料)について」を確認してください。
保育料の決定方法について
保育料は、子どもの年齢区分と父母等扶養義務者の市町村民税額の合計で決定します。ただし、同居の祖父母などが生計の中心者のときは、祖父母などの市町村民税額で決定することがあります。保育料は、下の関連リンク「保育所等保護者負担金(保育料)について」で確認してください。保育を利用できる時間帯を超えて保育を利用するときは、延長保育の扱いとなり、保育料とは別に利用料が必要となります。
保育料の切り替え時期
毎年9月が切り替え時期です。4月から8月分までは前年度の市町村民税額、9月から3月分までは当年度の市町村民税額に基づいて決定します。
注:子どもの年齢区分は、4月1日時点の子どもの年齢によって決定され、たとえ年度の途中で誕生日を迎えても、その区分は変わりません。
保育料の減免
次のようなときは、減免となることがあります。
- 同じ世帯から2人以上の小学校就学前の子どもが保育所などを同時に利用するとき
- 年収360万円未満相当の多子世帯の子どもが保育所などを利用するとき
- ひとり親世帯の子どもが保育所などを利用するとき
- 在宅障がい児(者)のいる世帯の子どもが保育所などを利用するとき
注:申し出なく保育料の減免の適用がないときは、さかのぼっての軽減適用や納付された保育料に係る差額分の還付を受けられないことがあります。
保育料の納付方法
保育料は保育所を運営するための大切なお金です。納期限までに、必ず納付してください。
口座振替
原則として、金融機関での口座振替により納付してください。(振替日は毎月25日。金融機関休業日のときは翌営業日)
町内の金融機関にある口座振替依頼書で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 通帳
- 金融機関に届け出ている印鑑
- 身分証明書
- 納付書
注:2人目以降の子どもが保育所に入所したときは、1人目の保育料を口座振替で納付していても、改めて手続きをする必要があります。
注:新規の口座振替の手続き完了までは1カ月から2カ月かかります。それまでは、納入通知書を送付しますので、納期限までに金融機関などで納付してください。
注:認定こども園、地域型保育を利用している人は、利用している施設に直接支払ってください。
納付書
バーコードが印字された納付書を使って、全国のコンビニやスマートフォンなどで休日や夜間でも、手数料不要で納付できます。
取り扱いコンビニ店舗や利用できるアプリについては、下の関連リンク「町税や料金の納付方法(コンビニ・スマホアプリ)」を確認してください。
コンビニやスマホアプリで利用出来ない納付書
- バーコードが印字されていない
- 納期限や納付予定日が過ぎている
- 1枚あたりの金額が30万円を超える
- 金額が訂正されている
- 汚れなどが原因でバーコードが読み取れない
副食費の納付方法
副食費は、施設に直接支払ってください。
町立中部保育所の副食費は、保育料と同様に口座振替または納付書でお支払いをお願いします。